いつもの朝。いつもの朝食。いつもの時間。
いつもの靴を履いて、いつものように家を出る。
だけど何故か今日の空は色を失くして、行き交う人々も表情がない。
いつもと同じ時間に家を出たのに、何故かいつもと同じ時間の電車に間に合わず、
私は無表情の人の群れの中、ホームのベンチに座った。
街ってこんなに温度を持っていなかったっけ?
すし詰めの通勤ラッシュはこんなにも人と人が密集しているのに、
そこには全く温かさがなくて。
ただただ己の頭痛と戦って、酸素不足の一歩手前でいつもの駅に降り立った。
誓い ep.5
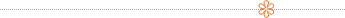
その日は夕方から雨になり、仕事を終える時間には雷も伴っていた。
朝から一日中頭痛と戦いながら、PCと睨めっこしていたが午後には吐き気までしてきて、頭が朦朧としていた。
「ダメだ・・・昨日飲みすぎた・・・」
給湯室で胃薬を飲む。
青臭い粉は封を開けただけで臭いが吐き気を誘う。
私は眉間にしわを寄せながら、それを一気に飲み干した。
「何?胃もたれ?」
完全に油断していた背後から久しぶりな声が被さってきた。
振り返るとなんとも給湯室の似合わないスラリとした男が、入口の暖簾を右手の甲にかけ、その手には更に似合わない昔ながらのポットを下げている。
「!関山さん!なんでこんなとこに!?」
「みりゃわかるでしょ?電気ポットの調子が悪くて・・・」
「関山さんのするような仕事じゃないでしょ!?」
「だって、みんな忙しそぉだし。」
「そんなの課の女の子に声掛ければいくらだってお湯沸かしてくれますよ。」
「そぉかな?」
「そぉですよ。」
関山さんと挨拶以外で会話をしたのはあの日以来だった。
自分でもびっくりするくらい普通に話せた。
きっと関山さんが普通にしてくれるから。
それにしたって相変わらずこの人自分がもてるって自覚してないなぁ・・・
彼は持っていたポットを台に置き、やかんに水を注ぎIHのボタンを押した。
私はとっととコップを洗って「それじゃ。」と給湯室を後にしようとした。
「本島さん、なんか変だよ?」
「え?」
「変。」
「なにがですか?」
「本島さんの顔が。」
「失礼ですね。」
よっていた眉間のしわを更に深くして私は自分の頬に手を当てた。
「や、言い間違えた。顔色が。」
やっぱりこの人はよくみている。
朝からずっと体調が優れないのに、隣のデスクの先輩だって私の体調の異変に気がつかなかったというのに。
「そぉですか?ただの二日酔いですよ。」
「・・・ならいいんだけど・・・?」
「?なんですか?」
「嫌、、、もしかして妊・・「してません!」
いきなり大声を張り上げた私を見て、関山さんは目を丸くした。
「チーフ、それセクハラですよ?」
ケラケラ笑いながら先輩が入ってきた。
よかった。余計な事言う前で。
「そぉだよな。ゴメン、本島さん。デリカシーがなかった。」
「いえ・・・」
関山さんは本当に私の体を心配してくれただけだったと思う。
それに異常に反応してしまう私の方がデリカシーにかけてた。
気にしてないふりしてても、そんなわけないってわかってるのに。
・・・それにしても、私が本当に関山さんとの子ども妊娠してたらどぉするつもりなんだろう?
ってか、2週間やそこらでわかるわけないって。
でも、本当にこれがつわりだったとしたら、それは間違いなく関山さんの子どもだ。
恭介とは・・・ここ半年何にもなかった。
なーんてね。そんな心配絶対ないし。月のものはちゃんと来てますよ。
黒いヒールには泥が跳ね、肩は傘では間に合わないくらいぐっしょりだった。
今日はなんて運のない一日なんだろうと毒づきながら、スーパーの袋の重みで動きにくくなってる左手を持ち上げ、
マンションのピロティーで私はかばんの中の鍵を探した。
春だというのに雨に打たれた体は冷え切っていて、鍵穴に鍵をさす右手の指先はかじかんでなかなか穴に通らない。
荷物が重くて微妙なバランスにたえるのはしんどくて、イラッとしたその時だった。
ピロティーホールの入口から床がたたき割れるんじゃないかというくらい甲高い音を立てて、見たこともない形相をして女が駆け込んできた。
頭から雨をかぶり、黒い長い髪は振り乱して顔に張り付き、でも、恰好はいつも通りのOLだった。
彼女は私の姿をとらえると、息を整えまっすぐに私の正面に歩み出た。
「どぉいうこと?」
いつもの彼女らしくない、ドスのきいた声だった。
幼稚園の頃からの付き合いだけれど、こんなに怒っている姿は初めてみた。
「な・・・何が?」
「何がじゃないわよ!?なんで稚々里くんに別れようなんて言ったの!?」
「!?なんで朱美が知ってるの!?」
驚いた。
昨日の今日だったから。
私はその話を誰にもしていなかった。
「・・・恭介に・・・会ったの?」
とりあえず私はじんわりと嫌な汗をかいた指先で鍵を回し、自動扉を開けた。
エレベーターを待っている時も、廊下を歩いている時も、朱美は妙に静かで私は奇妙な恐怖を感じた。
いつも穏やかな朱美が、こんなに怒って雨にも構わず、仕事帰りに怒鳴りこみに来るなんて、私にとっては天変地異だったから。
部屋に着くなり、私は慌てて彼女にタオルを差し出し、荷物を片づけた。
朱美はスーツを脱ぎ、ギリギリ無事だったブラウスの肩に髪をおろし、タオルで丁寧に拭く。
じんわり張り付いているストッキングには目もくれず、適当にスカートの雨水をはらって椅子に座った。
紅茶をいれて出しても、彼女は口もつけず、しばらく黙ったままだった。
私はそれを、判決を待つ罪人のように、彼女が口を開くのを待っていた。
外は相変わらずの大雨で、時々ピカッと光っては彼女の顔を照らした。
何を考えているのか見当もつかないその真っ黒な瞳は、ほとんど瞬きもせず、ただティーカップの水面一点を見ていた。
朱美が口を開いたのは、私が紅茶を出してから10分も経ったときだった。

skyblueさまへ。
クライマックスは慎重に・・・??
とりあえず完結編1です。
久しぶりの執筆作業は私の腰が持ちません。
何時間も同じ姿勢で書くのに集中力が持ちません。
だけど、ちゃんと構想は練っておりますれば・・・
今回はちょっと短めですが次回をお待ちいただければと思います。
本井 由癸嬢のみお持ち帰り可。
 →novel →novel
 →ep.4 →ep.4
 →ep.6 →ep.6
|